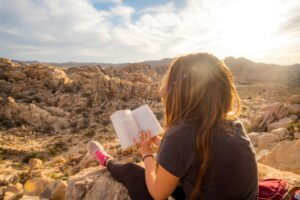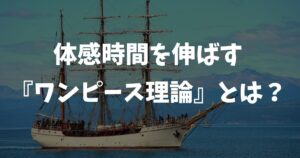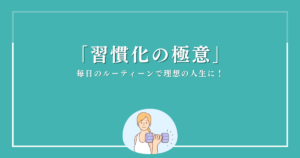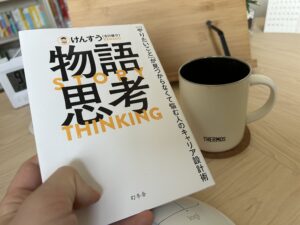「昇進を目指せ」「管理職を目指せ」
昭和・平成までは当たり前の価値観でした。
しかし、令和の今、その風潮に違和感を覚える人が増えています。
私自身もそのひとりです。
中間管理職の話が出るたびに、モヤモヤする。
なぜだろう?と自分に問い続けた結果、明確な答えが見えてきました。
それは「他人にそこまで興味がないから」です。
そして、これはあくまで私個人の感覚ではなく、今の時代を生きる多くの人が抱えている共通の気持ちではないかと思っています。
この記事では、なぜ中間管理職になりたくないのか、その背景にある価値観の変化、社会全体の傾向を紐解きながら、自分なりの働き方をどう見つけるかを考えていきます。
中間管理職になりたくない一番の理由は「他人に興味がないから」
私が中間管理職になりたくない最大の理由は、これに尽きます。
「他人にそこまで興味が持てない」
それだけです。
もちろん、最低限のコミュニケーションやチームプレーはできます。
しかし、人のキャリアを支援したり、日報を見たり、指導したり、評価をしたり…
そこに情熱を持つことができないのです。
管理職とは、言い換えれば「他人の仕事の責任も背負う立場」です。
部下がミスをすれば、自分の責任。
メンタルケアも必要。
評価や査定の不満をぶつけられることもある。
そういう「人を管理する仕事」に、自分は向いていないし、やりたいとも思いません。
昔は「昇進こそ正義」という時代でした。
しかし今は、そう思わない人がいてもいい。
組織の中で「管理職にならない選択」が許される働き方が、もっと認められていいと思っています。
令和時代は「昇進したくない」が多数派になりつつある
実際にデータを見てみても、この傾向は顕著です。
日本能率協会の調査(2023年)では、「昇進したくない」と回答した若手社員は約60%。
さらに、マイナビ転職の調査でも「部下を持ちたくない」「管理職にはなりたくない」とする人の割合は年々増加傾向にあります。
その背景には、いくつかの理由があります。
- 昇進しても給与が大きく上がらない
- 責任だけが増え、自由度が減る
- 管理職のストレスが大きいことが可視化されてきた
- SNSなどで副業やフリーランスの成功例を簡単に見られるようになった
かつては「上にいくほど給与も権限も増える」という明確なリターンがありました。
しかし現代は違います。
裁量が増えたように見えて、実際は社内政治や人間関係に時間を取られ、しかも報酬は微増。
そういった、事実がSNSなどを通じて見えるようになってしまっています。
これでは誰も「昇進の意味」を見出せなくなるのも当然です。
副業や個人活動の方が「自分の人生を生きている感」がある
私は会社員として働く一方で、副業にも力を入れています。
ブログ、ライティング、SNS運用。
さまざまなことに取り組んでいます。
こうした活動の中で強く感じるのは「自分で完結できる仕事」の快適さです。
誰かに指示されなくても、自分で選んで、自分で決めて、自分の裁量で動ける。
失敗しても自分の責任。
成功すればそのまま自分の成果。
実にシンプルで気持ちがいいのです。
副業をしている人たちと話すと、多くが「自分だけで完結する仕事の方が楽」と言います。
組織の中で、誰かの顔色を伺いながら動くよりも、よっぽど自由で楽しい。
だからこそ、あえて中間管理職を目指さず、個人の力で成果を出す選択をする人が増えているのでしょう。
「会社での成功=人生の成功」ではない時代が、確かに来ていると実感します。
【まとめ】これからは「昇進しない生き方」にも意味がある
もちろん、管理職として人を育てたり、チームで成果を上げることに価値を見出す人もいます。
それを否定するつもりは一切ありません。
ただ、それが「正解」ではない、ということです。
私は他人を管理するよりも、自分のパフォーマンスを最大化することに集中したい。
個人で動き、個人で価値を出す働き方の方が性に合っています。
だからこそ、中間管理職という立場を目指すことに、魅力を感じないのです。
とはいえ、個人で成し遂げられない壮大なゴールがあった場合などは、組織として動かないとむずかしいこともあるでしょう。
そういった野心がある人は、会社員として昇進も視野に入れて全力で働けばいいだけです。
令和の今、昇進を拒否することは逃げではありません。
自分の価値観に正直に働くこと。
その方がずっと生産的ですし、心も健やかでいられます。
「自分のペースで、自分の選んだ仕事に集中する」
そんな選択がもっと広まっていってほしいと思います。